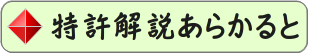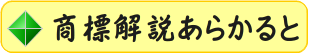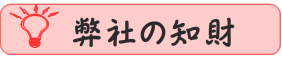代表取締役の小石川由紀乃から、サービスの紹介や雑感などを含めたメッセージをお届けします。
新規の企画を検討中の方々へのメッセージ
---必ず早めに商標や特許の調査をしましょう!---
あまり気の利いた表現ではありませんが、新しい企画を考えておられる方々や、いずれ企画される可能性がある方々に意識していただきたいことをストレートに表そうという趣旨で、上記のようなタイトル・副題を設定しました。
なお、「新規の企画」には「開業」も含まれます。開業の準備をされている方も、是非、以下をご一読下さい。

新しい商品やサービスを世に出すにあたり、知的財産についての検討も必要であると承知されている方は多いと思いますが、どうも、その検討は、商品やサービスの内容がほぼ定まってからになり、検討の対象も特許や商標登録の申請をすることに限られることが多いと感じます(あくまでも私の乏しい経験による推測ですが・・・)。
勿論、大事な知的財産を守るために特許や商標登録の申請をする必要は大いにありますが、
申請の手続きより前に意識すべきこと、早い段階から取り組む必要があることがあります。
それが調査です。
この必要性を意識していないと、将来、やっかいな問題が発生する可能性があります。

たとえば、商標の場合、企画を詰めてゆく過程で商品やサービスの名称やロゴマークのデザインを検討することが多いでしょうが、それらをなんの調査もしないで決定してしまうと、登録が困難な商標(拒絶理由が通知され、その解消に時間がかかる。)を選択してしまうおそれがあります。
他社の登録商標に非常に近い商標を選択してしまうと、登録は一段と難しくなる(拒絶理由を解消できない可能性が高まる。)うえに、実際に商標が付される商品の種類によっては、相手方から、「商品の混同が生じており、当方の商標権を侵害している!」という指摘を受ける可能性も生じてしまいます。
商標は、殆どの分野の事業者に関係がある知的財産です。
特に、新しい事業を計画されているときは、名称やロゴマークを検討されるケースが非常に多いと思われます。その検討の際には、名称やロゴマークを決めてしまう前に調査を行い、登録の可能性が高いと思われるものを選択する・・という意識を持って下さい。
特許に関しても、
すでに特許された発明や特許出願中の発明(特許される可能性があるもの)の中に、開発中の商品・技術に近いものがないか・・・という観点から調査をする必要があります。
特に、類似する先行の商品がある場合や、シンプルなものだが世の中にまだ出ていないと思われるものを企画している場合には、調査は必ずしていただきたいと思います。

類似する先行の商品やソフトウェア技術が絡む類似のサービスがある場合には、言わずもがな、その先行の企業が特許等の権利を取得または出願をしている可能性がありますので、最低限、それを確認する必要があります。
先行の企業の権利や出願が見つからなかった場合でも、その企業の関係者(個人)や他の企業の名義の特許や特許出願が存在する可能性がありますので、権利者や出願人の条件を外して調べることをお勧めします。
仕組みや形態が簡単なものは、ヒットした場合に模倣される可能性が高いので、防衛目的にとどまるとしても特許の申請(出願)を検討すべきです。
そのときに邪魔になるのが、「この程度のものが特許になるはずはない!」という思い込みです。
簡単なものであっても近いアイデアが世に出ているという事実が認められない限り、特許を受けられないとは言い切れません。
特許の審査で新規性や進歩性がないと判断するには、その根拠となる先行技術を示さなければなりません。このことをふまえ、調査で新規性や進歩性がないことを示す先行技術を見つけることができなかった場合は、「特許を受けられる可能性があるかもしれない」と考えても良いと思います。
一方、類似のアイデアが見つかった場合には、同様のアイデアを出願しても特許を受けられる可能性は殆どないと思われるので、出願する意義はないと思います。
類似のアイデアがすでに出願されていることに早い段階で気づけば、特許申請をしたいと考えていたとしても、 諦めて他の方法による保護を検討するか、特許申請が可能なレベルになるように企画を練り直すことができます。
類似のアイデアで特許を受けているもの、特許される可能性があるもの(特許庁に係属中の出願)が見つかった場合には、 その権利を侵害することがないよう、仕様の見直しをすることができます。

特許の検索では、たいてい多数の特許文献が抽出され、それらの内容を1点ずつチェックする作業に多大な時間がかかります。重要度が高いのに検索の条件にあてはまらずに抽出できない文献やまだ公開されていない出願が存在する可能性もあるので、どれだけ念入りにチェックしても、完璧な結果が得られたと言いきれません。
かくのごとく、特許の調査には”どこまでやっても完璧と言えない・・という頭の痛い問題がありますが、それでも、全く調査をしない、あるいはたまたま知った1~2件の特許との比較だけで計画を進めても大丈夫、と判断するのは非常に危険です。
個別の事情に応じて「これだけは確認する必要がある・・」と言える条件をもって検索をかけ、調査の対象分野にマッチする内容の文献を抽出することができれば、かなり信頼度の高い調査結果を得ることができ、侵害等のリスクを減らすこともできると思います。
煩雑になるのを避けるため、重要度が高い特許と商標の調査についてのみ述べましたが、 企画の内容によっては意匠の調査をする必要もあります。
また、 特許の調査は、たいていは実用新案まで対象に含めて行います。実用新案の登録公報は、特許の出願公開公報と同様に、類似のアイデアを示す先行技術文献として機能するからです。実用新案権は無審査で登録され、権利行使にも制約のある権利ですが、それを理由に実用新案権なら抵触しても構わないと考えるわけにはゆかず、類似のアイデアで実用新案登録を受けているものが見つかったときは、その内容を精査する必要があります。
いずれの調査も、早い段階で行うことによって、計画をそのまま進めて良いか、軌道修正が必要かなどの判断をしやすくなり、他者の権利を侵害してしまう可能性を低くすることができると思います。
どうか、知的財産についても抜かりなく検討できた企画をたて、成功を目指して下さい。
特許庁の検索サイト(J-Platpat) *は誰でもアクセスできて、自由に検索をすることができますが、本格的な調査をするには、特許,商標等の制度や検索手法に関する知識と実務経験が必要です。
特許について確度の高い調査をするためには、 特許分類を使用するのが望ましいです。
件数の絞り込みのためにフリーワードを入れる場合も、 どの項目を選択してどのようなワードを入れるかの検討をする必要があります。
検索で抽出された個々の文献(特許、実用新案等の公報)の内容が調査対象に関係あるかどうかを判断する作業も必要です。
商標の検索も、使用される予定の商標の表記だけでなく、 商標から生じる読み(称呼)を入れて 類似レベルまでの検索をする必要があります。商標を使用する予定の商品やサービスに検索の範囲を絞り込むために、 類似群コードと呼ばれる分類コードを特定する必要もあります。
*J-Platpatは、正確には、独立行政法人工業所有権情報・研修館により運営されています。
調査が必要であることや重要性はわかるが、
本格的な調査をする力や時間的余裕はないし、外部に委託するために多額の費用を投じる余裕もない・・・
検索の結果をどのように判断したら良いかわからない・・・
というようなお困りごとがある場合には、いちど弊社に相談してみてください。
株式会社知財アシスト
代表取締役 小石川 由紀乃 (弁理士)
新年最初のメッセージ

あけまして、おめでとうございます!
コロナ禍の中での活動もまる2年になりました。
新しい変異株への感染者もじわじわと増え、油断できぬ状況ではありますが、できる限りの取り組みをしてゆこうと思っています。
コロナのおかげでひとつ有難いと思えることがありました。
リモート面談でご相談を承ったり、打ち合わせをする機会が増えたことです。
遠方の、それも一度もお目にかかったこともない方とのリモート面談も、なんども経験しました。
リアル面談と全く同じように・・とまではゆきませんが、詳細なご事情を伺ったり、ご質問へのご回答やご説明をスムーズに行うことができました。
なにより、お互い、顔を見ながら声を届けることで、親近感がぐんと高まりました。
事案によっては、リアルでお目にかからないと対応が難しいこともありますが、少なくとも初回のご相談ごとを承る分には大きな差支えはないと感じました。
この成果をふまえて、遠方の方用のサービスを主目的としていた電話相談「テルソー」をサービスメニューから外し、リアル面談を原則としていた知財よろず相談にリモート対応を加えることにました。
リアル・リモートのいずれでも、初回のご相談は、よほど長時間にならない限り、無料で承ります。知的財産に関して何かの問題を抱えておられる中小企業や個人事業者の方、新規事業を始めるにあたって知的財産の保護や活用についてのアドバイスが欲しいとお考えの方は、是非、知財よろず相談の利用をご検討ください。

もうひとつ、嬉しいことがありました。
遠方からご連絡を下さってリモート面談をさせていただいた、とある企業の経営者の方に、
「ウチのようなちっぽけな会社を、どうやって見つけて下さったんですか?」と尋ねると、
「小石川さんが書いているものを読んだからですよ。」
と言っていただいたのです。
知財のことで色々と調べているうちに私が以前に書いた解説記事(知財ブログ)を見つけて下さり、会社情報やサービスの案内も見て、関心を持って下さったようです。
新作記事を殆ど投稿できていない時期にもかかわらず、そのようなお言葉をいただいて気恥ずかしい思いをしながらも、情報発信をすることの大切さを改めて認識しました。
これまでは、まとまった時間がとれたときに書こう・・と後回しにし、その結果、いつまで経っても書けずにおりましたが、僅かな時間でも記事の原稿を書くことを日課にしようと決意し、昨年の終盤より、ようやく、実践できるようになりました。
要領が悪いうえにこだわりが強いもので、ほんのわずかな分量の記事を一本まとめるだけでも相当の時間がかかり、ほんのたまにしか投稿できないとは思いますが、それでも、全く書けていなかった頃よりは多くなると思います。
またサボって書かなくなるのを防ぐため(?)に、特許、商標の別に、目次のページやそれらへのリンクボタンも作りました。
弊社の自前の知財の紹介記事も、できるだけ増やしてゆこうと思っています。

本年も、志と責任感をもって、
そして、へこたれずに活動をしてまいります。
どうかよろしくお引き立てのほど、お願いします!!
株式会社知財アシスト
代表取締役 小石川 由紀乃 (弁理士)
改めて「ここでん」のこと
もう5年ほども前のことになります。
大勢の人が行き交う阪急うめだ本店前のコンコースで、柱の陰にしゃがみこんで電話をしているスーツ姿の女性をみかけました。

営業職らしいその女性は、自分のひざの上に紙を広げてメモをとりながら小声で一所懸命に話をしていました。周囲の音の影響で先方の声も聞き取りづらいでしょうに、よほど急ぎの要件で落ち着いて電話ができる場所を探す余裕もなかったのかも知れません。
なんとも気の毒な光景でした。
このとき、すでに、後述するビジネスモデルの原案が頭にあった私は、この女性を見て、
「こんな人の役にたてるよう、なんとしてもこのビジネスモデルを実現させたい!」
と強く思いました。
その後も似たような光景に遭遇する都度、また自分自身も出先で電話をかけねばならない事情が生じる都度、その思いが蘇りました。具体的なチャレンジを開始してみると、とてつもなく大きな壁があるとわかり、何度も挫折しかけましたが、不思議なご縁で繋がった方々からお力添えをいただき、細々ながらもアイデアを具現化させるための取り組みを続けてまいりました。
メールやSNSが主要な連絡手段の地位を占めるようになったとはいえ、急ぎの連絡やこみいった内容の相談などをする必要がある場合には電話が欠かせません。

しかし、多くの人が行き交う場所はどこもかしこも賑やかで、相手の声が聞き取れず、自分も大声を出さないと相手に伝わらないなど、通話に支障が生じることが多々あります。
また、仕事関係や重要な要件の電話では、冒頭の話の女性のようにメモをとったり、資料やパソコン操作をしながら話をする必要がある場合が多く、それらの作業が容易に行える環境が必要です。
他人が映り込まない場所でラインやスカイプなどのビデオ通話を行いたい人もいることでしょう。
人に聞かれたくない話だが、できるだけ早く連絡をとらなければならない・・というような事情を抱えた方もおられると思います。

電話やビデオ通話に限らず、移動中に入ったメールに急いで詳細なコメントを返したい人、スマホに入ったメールに添付されている資料をパソコンの画面でしっかり確認したい人など、重要または緊急性の高い作業をするのに適した場所を探している人も、きっとおられるはずです。
これらの事情を抱えた人たちに、
落ち着いて電話やメール連絡や事務作業などを行うことができるスペースを形成するブースを、
予約や会員登録の必要なしに、少しだけ料金をお支払いいただくことで、
誰でも利用できるようにする仕組み・・・
これが弊社・知財アシストが考えたビジネスモデルです。
「ここで電話できるよ」というメッセージを込めて、
ブースの名前を「ここでん」(漢字表記は「此処電」)と名付けました(商標登録済みです。)。
コロナ禍でテレワークが推奨されたり、感染予防のために緊急事態宣言が何度も出されたり延長されたりしても、一向に減らない人流の中には、動かなければならない仕事や大事な用事を抱えている人がたくさんおられると思います。それらの人たちの中には、電話やメールでの連絡や短時間の作業をするための場所を探している人が、少なからずおられるはずです。

弊社のビジネスモデルは、これらの方々が抱える不便を解消して活動しやすい世の中を作ると共に、多くの人が行き交う場所でも密にならない環境に一定時間留まって電話やPC作業を行えるようにすることで、感染対策にも貢献できるものです。
コロナ禍で停滞した経済活動を活性化させるには人々が活動しやすい社会にする必要があり、そのためにも、できるだけ早く、このブースのプランを実現させたいと思っています。
あるお方の問題提起から浮かんだ思いつきにすぎなかったアイデアが、ソフトウェア関連発明として特許を取得できるまでの内容に進化し、その特許発明をベースとする管理システムを入れたモデルブースも、このたび完成しました。



資金も開発能力もない超零細の弊社がここまで進むことができたのも、「ここでん」のコンセプトに共感して下さった大勢の方々の声援やお力添えのおかげです。
皆様に、心よりの感謝を申し上げます。

さらに先に進むには、もっと大きな力が必要です。
実際のビジネスを担っていただくための力もですが、
「ここでん」があると助かるのになぁ・・・
「ここでん」を早く利用したいなぁ・・・
というつぶやきも、実現可能性を大きく膨らませる力となります。
どうか、下記の関連記事を合わせてお読みいただき、
共感できると思われたならば、
「いいね!」ボタンのタッチやシェアなどの方法で
応援してやって下さい !!
株式会社知財アシスト 代表取締役 小石川 由紀乃